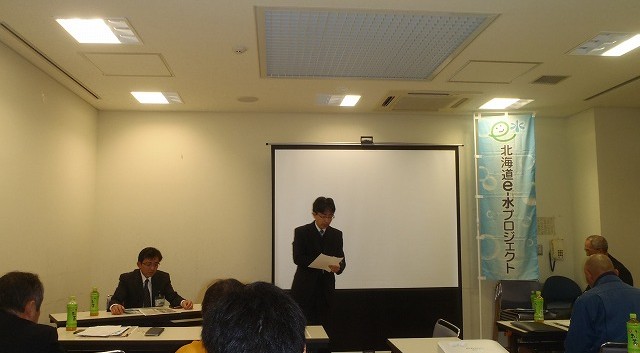Webレポート
環境DNAを用いた北限域のアユ資源と外来生物の分布調査
【黒松内町】後志地域生物多様性協議会 Webレポート
団体名:後志地域生物多様性協議会
事業名:環境DNAを用いた北限域のアユ資源と外来生物の分布調査
後志地域生物多様性協議会は北海道e- 水プロジェクト助成金を頂き、後志地域の主要な 10 河川及び 洞爺湖の 28 箇所から採水し、サンプル水に含まれる環境 DNA を解析することにより、北限域のアユと ウチダザリガニ等の外来生物等の分布状況について調査しました。サンプル水を濾過して含まれている DNA を濾紙に固定。冷凍保存した濾紙は北海道大学荒木研究室、兵庫県立大学土居研究室で DNA の増 幅(PCR)、ターゲット種 DNA との比較検討、解析等を行いました。 生物多様性の保全と持続的な利用について様々な活動が展開されていますが、活動の方向性を検討する 際には、外来種や希少種をはじめ多様な野生生物の生息状況を正確に把握することが最も重要です。特に、 水中のモニタリング調査には多大な労力と専門性、長期間にわたるコスト負担が求められることから、緊 急性などが高い調査に限定される傾向がありました。今回、新たに試みた環境 DNA を用いる調査では、 短期間かつ正確に、低コストで多様な生態系の広域的把握が可能となりつつあります。
環境 DNA 分析の特徴として同一サンプルから複数のダーゲット種を検出することが可能なので、北限 域のアユ分布について広域的に調査しつつザリガニ 2 種と同時多魚種検出を行いました。平成 28 年の 全国利き鮎会では朱太川産(黒松内町)天然アユがグランプリを獲得し、その食味の良さが認められてい ます。従前から余市川産アユが食用として利用されてきましたが、北限域に位置づけられる後志地域でど のような広域分布をしているか充分には把握されていませんでした。調査した 10 河川のうち余別川を除 く 9 河川からアユ DNA が検出されたことから、北限域のアユが地域全般に広く分布しており、将来的に 地域を代表する内水面水産資源としての活用が期待されます。アユの寿命が 1 年間である事から毎年変 動すると見込まれるアユ資源量の把握について、継続的な環境 DNA 調査が有効であることが示されまし た。
同時多魚種検出では地域全体の総検出数が 25 種に増加し、将来的に各河川の「さかな図鑑」の作成に 繋がる成果となりました。また、尻別川水系のみでイトウが僅かに検出され、分布は限定的と推測されま す。今後も尻別イトウの分布拡大を促進するオビラメの会との継続的な連携が求められます。
北海道に食用として導入され、現在も分布を広げている特定外来生物ウチダザリガニは、後志地域に隣 接する洞爺湖に定着し防除活動が継続的に行われています。後志地域への侵入を想定し、初期段階で効果 的な防除活動を展開することを目的として、平成 28 年度から継続して分布調査を実施しました。平成 28 年度の調査では両ザリガニの DNA 検出が困難でしたが、濾紙の改善など検出感度を高める改良によ り、洞爺湖水からウチダザリガニとニホンザリガニが検出されました。また、後志地域からウチダザリガ ニの検出は無く、侵入は確認されませんでしたが、ニホンザリガニが検出されたことから、複数箇所での 生息の可能性が示唆されました。今後は両ザリガニをより明確に検知するための河川流量・流速などに採 水条件の再検討が必要になります。
本事業の一環として、11 月 18 日に札幌市環境プラザ、11 月 20 日に後志総合振興局において勉強 会を開催し、調査結果と今後の課題などについて関係者及び一般の皆様と学習しました。また、環境 DNA による生物分布調査の利点と課題についてパンフレットを作成し、当協議会構成団体に配布すると ともに、今後は環境展示会などでパンフレットを配布し、e- 水プロジェクトの支援によって得られた環 境 DNA に関する最新の知見について広く周知する予定です。
後志地域生物多様性協議会

後志地域生物多様性協議会
環境DNAを用いた北限域のアユ資源と外来生物の分布調査

 CONTACT
CONTACT